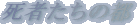
枯れかけた木々がまばらに生えた岡の上に、一人の少女が立っていた。
黒髪は後ろで一本に束ねられ、黒い長衣にマントと、典型的な魔術師の姿をしている。漆黒の瞳は、高い城壁で囲まれた都市を映していた。
眼下の街並みは他の国のそれとはまったく異なっていた。家がどれも大きく、そして形がいびつだった。まるで、どの家も手当たり次第に増築しているようだ。壁の色形も様々で、それぞれの家の者の好み次第のように思える。
それに、それは事実なのだろう。岡を下り、門をくぐった少女は、壁にかけたハシゴに登って大工仕事をしている男を視界に捉え、そう結論付けた。
(まるで、国中が増築中のようだね。一体なんだと思う?)
少年の声が、少女の頭の中で響いた。少女はその声に、小声で答える。
「シゼル。住むところがたくさん必要ってことは、人口が増えてるってことじゃないか?」
(そのわりには、人の姿が少ないけどね)
シゼルは、辺りを見回す少女の視界を共有しているようだった。
映像を伝える〈ビジョン〉と音声を伝える〈テレパシー〉という魔法は、一般の人々にとっても馴染みの深い魔法だ。遠くの場所への通信手段としてよく併用されるが、両方を長い間持続させるにはかなりの実力が必要とされる。
そして、少女はその実力を持っていた。セティア・ターナーの名は、白魔法と黒魔法を両方収めた大魔術師の名として知られ、恐れられている。
しかし、さすがに顔はそう知られているわけではない。
「お嬢さん、旅の人かね?」
通りを行くセティアに声をかけてきた白髪の老人も、特に相手の正体に気づいた様子はなかった。
「はい。見聞を広めるために旅をしています」
「そうか……もしよければ、家に泊って行かないか? たまには生きた話し相手が欲しくてな……それに、近くの宿は増築中だから」
老人は必死にセティアを自分の家に連れて行こうという様子だった。おそらく一人暮らしなのだろう。話し相手がほしくて仕方がないに違いない。
(シゼル。どうする?)
いちいち指示を求める必要はないが、セティアとしては、雇い主の意志を尊重するつもりらしい。彼女は頭の中で、テレパシーの送信先にきいた。
シゼルは予想通りあっさりと、老人の申し出を受け入れる。
(こっちも、この様子じゃすぐに話し相手捕まりそうにないから、いいんじゃない?)
「……では、お邪魔します」
セティアがどこか事務的に返事をすると、老人はさも嬉しそうに彼女の手を取り、何度もお礼を言った。
その様子を、少し離れたところから、一人の少年が見ていた。
旅人の手を引いて家に戻ると、老人は彼女を居間のテーブルにつかせ、張り切った様子で厨房に入っていった。昔、レストランで料理長をやっていたのだという。
テーブルにひじをつき、辺りを見回しながら、セティアは溜め息を洩らした。
「落ち着かないな……」
家は、広かった。五人家族で暮らしていたとしても充分なほどの広さがある。
(おもしろい家だね。童話に出てくるキノコの家みたい。しかも、毒キノコ)
「カラフルだからな……」
ドアがなく、この部屋の八方にある出入口から、それぞれの部屋が見える。一つは、老人が料理を作っている厨房だ。それを含めたすべての部屋の壁が、それぞれ違う色に塗られていた。
「息子たちはこの街を出て行ってしまってねえ……妻も、二年前にはやった病で逝ってしまった」
エプロン姿の老人は、サラダと自家製らしい青緑のジュースをセティアの前においた。
「まあ、寂しくはないが、たまには生きた人間と会いたくなる。自分が生きているのかどうか、確かめたくなるのかもしれないな」
テーブルの上に、次々と料理が並べられていく。サイコロステーキや、パイ入りシチュー、白身魚の香草蒸しが食欲をそそる匂いをかもしだす。
セティアは、それが全部食べられるかどうか心配になった。
「さあ、遠慮せずにどうぞ」
「……いただきます」
不安なまま、フォークとナイフを手に取る。その心境を知らずに、シゼルがふてくされたようにつぶやいた。
(ずるい)
シゼルは、食べたい物も食べられない状況にある。それは不幸なことだが、こちらにも少しは同情してもらいたい……そう思いながら、セティアはサイコロステーキのひとかけらを口に運んだ。ほどよい甘味と辛味が舌の上でとろける。
「おいしい」
思わず感嘆のことばが洩れる。彼女はしまった、と思ったが、それを聞いた老人の嬉しそうな顔を見て、シゼルの沈黙は気にしないことにした。
「どれも、この地方の名産物を使ったものだ。他の地方の名物料理にも負けていないだろう?」
ここに呼ばれたのは、話し相手になるためだ。各地を旅する彼女なら様々な土地の話を知っているだろう、と、期待されているに違いない。
このおいしい料理の礼に、旅の話くらいしてもいいだろう。
セティアは、シゼルのことは伏せて、今までの旅のことを話して聞かせた。それを、老人はうんうんうなずきながら、楽しげに聞いている。
食事が終わるまでの間、シゼルは黙っていた。
老人はセティアに、好きな部屋を使っていいよ、と言った。セティアは紺色の壁の部屋を選び、まず、何もない出入口に毛布でドアをこしらえた。
ベッドは、かなり長い間放っておかれたようで、かび臭かった。老人が持ってきたシーツと毛布に取り替え、もとのシーツを窓の外ではたこうと思い立ったところで、彼女はこの家で窓を見かけないことを思い出す。
「壁にこだわってるんだろうか……」
とりあえずシーツをたたんで隅に置き、マントと荷物をベッドのそばの机にのせる。彼女が魔法の発動器にしているのは、青白い聖水が入った雫型のペンダントだ。それは、入浴中でさえ肌身離さず身に着けている。
すでに、外は夜闇に満たされているだろう。ベッドに身を投げ出し、彼女はあくびをした。
(……ここの人たちは、明るいのが嫌なのかな)
「シゼル、起きてたのか。寝たのかと思った」
(起きてるよ。セティアがおいしいご馳走を食べている間もね)
恨めしげなことばに、セティアは苦笑した。
「ちゃんときみの分まで味わって食べるのが私の義務じゃないか?」
(ああそうかい、ご苦労さま。それより、この家の構造、おかしくないか? なんか、外から見た時と比べてみるに、壁が厚い気がする。まるで監獄だ)
セティアは、ベッドから立ち上がって紺色の壁に歩み寄った。燭台のロウソクが揺れ、小柄な影を映し出す。
壁を軽くノックしてみる。コツコツという小さな音が鳴った。どこか外観から予想できないような音に、セティアは顔をしかめる。
「確かにな……何かつまってるような。それに、何か妙なにおいがする」
(におい?)
さすがに、シゼルは嗅覚までは共有できない。しかし、セティアのほうは、かすかに壁際に漂う、あまりいいにおいとは言えない刺激を鼻腔に感じていた。
「どこかで嗅いだような……」
不意に、彼女はことばを途切る。
誰かの声が、その耳に届いた。この家のなかにいるのは、彼女と、あの老人だけだ。
「……な、たまにはいいだろう。わしだって他の者とも話したいよ」
それは、確かに老人の声だった。その声に引かれ、そっと出入口に歩み寄る。
「それは、わかっているとも。だが、いつもそうするわけにはいかないだろう」
かすかに聞こえる声は、老人のものだけだ。
(誰と話してるんだろう……)
「案外、テレパシーだったりして」
自分たちも、奇妙に思われているのかもしれない。そう考えて、二人は少しの間、黙った。
声は、何かに反論しているような調子で続いていたが、やがて途切れた。ロウソクを吹き消し、セティアとシゼルも間もなく眠った。
深夜、セティアは、何者かが動く気配で目を覚ます。
反射的に薄目を開けてみると、闇の中で、何かがキラリと光ったのが見えた。
「なに……」
自らベッドから転がり落ちた彼女は、横目で、シーツが引き裂かれるのを視界に捉えた。それに、右手にした使い込まれた包丁を振り下ろした、男の姿も。
それは、確かにこの家の主人である老人だった。
(セティア?)
異変で目覚めたシゼルが不安げな声をかける。セティアには答えるが余裕なく、ベッドの上に足をかけようとする相手に枕を投げつけながら、自分の荷物を引っ張り、片腕に抱えた。
「頼む、大人しく人壁になってくれ!」
ベッドを挟んだ向こうで、老人が懇願するように叫ぶ。
(ジンヘキ……?)
「人柱なら聞いたことがあるけど」
人柱、とは、人間を建造物の壁や柱に塗りこむことだ。すると、霊がその建物の守り手になると伝えられていた。
昔、ある地方で行われていた風習である。
「似たようなものだ。この街では、人が死ぬと家の壁のなかに塗り込められる。それが家の守護霊になるんだよ」
スキを見て回り込もうと、相手を油断なく見据えながら、老人が説明する。セティアは当然、簡単にスキを見せたりはしない。
「それで、家の増築を……しかし、なぜ、わたしを」
「他の者の力、特に強力な者の力が家のなかに入れば、守りの力が強くなる。最近、また病が流行っていてね、毎日のように死人が出てる。わたしの子どもたちも危険な状況なんだ」
死人が出るほど増築も増えるのだから、被害はかなり深刻なものだろう。昼間見た街並みの光景を思い出し、セティアは思っていた。
「頼む、子どもたちのために死んでくれ!」
老人はベッドに足をかけると、バネを利用して、一気に跳びかかった。
セティアは突き出された包丁の切っ先をかわし、空いている左の手のひらを突き出す。空気の塊が老人の脇を叩き、軽く壁に叩きつける。あまりしっかりしていない壁がドシンと揺れ、表面にひびが入った。見た目は派手だが、シゼルには、一応手加減したことがわかる。
老人の手から、包丁が飛んだ。
恐怖の表情で見上げた目に、マントをまとった魔女が映る。
「おいしいご飯、ありがとうございました。わたしはもう行きます。奥さんによろしく」
早口に言い捨てて、旅人は部屋を出て行く。
痛めた腰をさすりながら老人がリビングに向かうと、自分の寝室の壁に割れ目ができているのが見えた。
割れ目からは、白骨化した人間の顔の一部がのぞいている。
老人はそれに近づくと、うなだれてつぶやく。
「すまない、お前……」
ポーチを着けたベルトを腰に巻き、リュックサックを背負いながら、セティアは闇に紛れて門に向かっていた。
(この街で、何人の旅人が亡くなったんだろう……)
「そのなかの一人には数えられたくないな」
幸い、通りには人の姿がなかった。しかし、待ち伏せするなら門だろう。セティアは警戒を緩めることなく、門に歩み寄る。
そこには、人影があった。だがそれは予想外に小柄な相手である。
こちらに気がつくと、その人物は月光の下に歩み出てくる。強い意志と、怯えを目に宿した、十代前半くらいの少年だった。
彼はセティアの顔を見ると、ためらいがちに口を開く。
「あの……お願いです、妹の病気を治して欲しいんです」
「人壁はごめんだよ」
素っ気なく脇を通り過ぎようとするのに、少年は必死に食い下がった。
「違います。大人たちは、人壁が必要だ、祖霊のお告げだって言ってるけど……守護霊より、魔法のほうが凄いんでしょう?」
少年の瞳には、期待の色が見える。
黙っているセティアの頭のなかに、シゼルの思念が響いた。
(ねえ……何とかならないの?)
彼はまるで、少年の心を代弁しているようだった。
セティアは声に出さずにことばを返す。
(彼に同情しているのかい?)
(ボクにも昔、妹がいたからね……)
セティアは首を振った。
「あいにく、治すような魔法は覚えていない」
期待を持ってことばを待っていた少年の表情が、はっきりと落胆に変わった。シゼルの思念も、ガッカリした調子を表す。
セティアは無感情に彼を見返した。
「病気を治したいなら、まずはこの街を出ることだ」
「でも……」
唐突なことばに、少年は顔を上げる。
「それができないなら、家を燃やすんだね」
肩をすくめて、魔女はマントをひるがえす。
少年は茫然と、門の向こうに遠ざかっていく後ろ姿を見ていた。
次の街まで、数時間の距離だった。セティアは野宿より、歩き続けることを選ぶ。草原の中の一本道は、普段は遮るものがないはずだが、今は霧がかかっていた。月光に照らされた霧に包まれた周囲は、どこか神秘的ですらある。
(あの老人、誰と話していたんだろう? 守護霊?)
「やっぱりテレパシーに近いものかもね」
興味なさそうに応じて、後ろを振り返る。霧のために、門はとうに見えなくなっていた。
「どんな人も……相手によって、共感の能力を発揮するものらしいしね」
独り言のようにつぶやき、視線を上に向けたそのとき、彼女は、一筋の煙が立ち昇っているのを見つけた。
(あれ……あの街から?)
煙は、やがて夜空にいく筋もの白い線をひいた。
それが夜空を埋め尽くし、霧と混じり合ってそれとわからなくなるころ、再びセティアは歩き始めた。